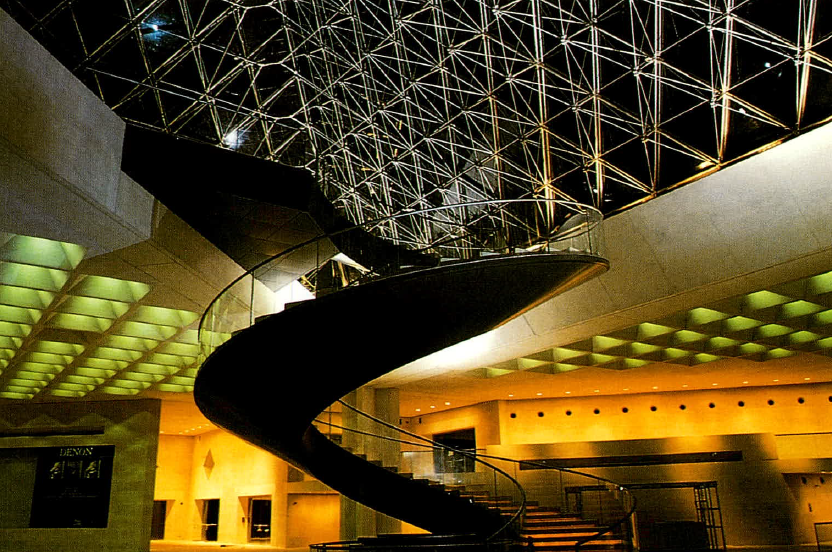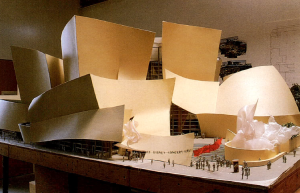情報通信社会で、情報提供業で食うために、面白い情報を伝えることは肝要だ。では、何が面白いだろうか。伸びない理由は簡単である。得た断片を述べ並べ、断片それぞれに感想をつける、のを流すだけでは、調査力のある情報要求を満たせない。なぜなら、その情報検索は、鍵語のひとつでも得れば、自分で収集できるからだ。検索すれば済むものは生成知能に任せてしまえるし、浅い提供者の情報は浅いだろう、といういわゆる安かろう推論が、物質だけでなく情報にも適用できてしまえるからだ。実際、浅い情報源から有益な情報を取り出すことは、むしろ難しい。
話題があり、それについて語り合いたいだけであるなら、語りたい友人性が必須である。だから、この系の情報提供者は、みなフレンドリーである。しかし、気を付けなくてはならないのは、彼らこそ情報を欲していることだ、それで生計を立てているのであるから。なので、情報提供に関する不均衡がここに発生している。情報にお金を払っても、受け取った側が情報も受け取ってしまう。つまり、参加者はお金を払って情報まで提供する、という情報搾取の構造が生まれてしまっている。情報の拡散源として言及してくれる人ばかりでもない。
事例をたくさん出す系の情報提供業者を、生成知能の活用者は見向きもしない。ラジオとして聞くだけであろう。ぐだっているくらいがちょうどいい日の後景音源としての価値はあるからだ。そして、そもそもインターネットは場所だけ自由にした構造なので、上げた情報がどのような人につながり、誰に知られ、どのようなエコロジーが存在するのか、普通には知られない。それに、情報の消費には時間が必要なので、みな情報を短時間で濃く得たいと考えるが、情報同士を結合させる思考の速度はむしろGPUのように遅くないといけないので、多くの情報を短期でぐるぐる収集しても、記憶に移行する情報は1%もあればいいところ、多くはCPU的な発熱に使われるだけで消えてしまう。それに費やした時間も。当然、つまらない話に感じるわけだ。
記憶に残るには、不揮発性記録のように書き込まねばならない。そしておそらく、普段から情報を浴びるように視聴している人は特に、ひとつかふたつ、書き込めれば、十や百は思考が展開するのではと思う。書いたり作ったりする技術を持った人はいくらも練れるし、作り方に関心のある人には、検索するだけでも身につけかたはわんさか見つかる。環境を整えたいと思ったら、動画ではわからなくても地域や知人に知っている人はいるだろう。情報で食べることは、あふれた情報の中においては大変で、薄利は確定と思ったほうが良い。しかし、正しい情報には必ず読者がつく。価値があるからだ。その他のどうでもよい情報に価値を与える情報が、私が好きな情報だ。どんな情報も、偽誤性にかかわらず面白く見ていられるからだ。