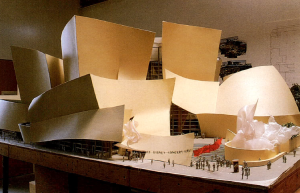「論理哲学論考」を初めて読んだのは,高校3年18歳の秋だった.この頃に読んだ本は今の私にそのまま濃い影響を残しており,この読書の時期によって私は数々の性質を失った.育っていた数々の特徴が壊れて消えた.代わりに,人とは異なる特殊な性質を見つけられたし,それを今に至るまで養ってくることができた.失っただけ得た.だから,この本を含め,読書に対して感謝もあるが,憾みもあるし,本との出合いの数奇さを思わされる.高校3年で最後まで読んだ上,簡単な小論を書いてウェブに公開したものだった.高校3年での見解は荒削りだったが,今に至る私の見解につながる部分もあり,若い時の挑戦も無駄ではないのだなと思う.
さて,ここまで読み込んだこの論考である.当時は数冊しかなかった解説書も今では色々出ていて,内容を引き比べようと思えばできる.しかし,私は自分の見解を述べる.なぜなら,私の脳内で引っかかり続け考え倦ねた末の見解を持てたからだ.この見解を確かにしたら,他の考察と照らしたいとは思う.まずは私の見解を自分で語れるようにしておきたい.
「世界とはその場に起こることの全てである」ので,私はしばしば,確率論を考えた.その場でどのくらい起こりそうか,という量があることは,世界にとって大きなことだと思うからだ.「その場で起こされることも,その場では起こらない全てのこと」も,世界はすでに決めているからだ.ここから簡単に推論できるのは,世界は決定論であり,この本では偶然性を重視しない.それで「世界とは事実の総体であって,事物の総体でない」というこの一文が,私はずっと引っかかった.確かに「世界は,諸々の事実によって,そしてそれらが全ての事実であることによって決まる」のだろう.だから私たちは世界を決めている事実を探究していこうと動機づけられる.しかし,世界はものの集まりではないのか.私は単なるものでもないとは思うけど,宇宙に散らばる無数の天体や,机の上に積み重なる本の束や,鍋でぐつぐつ煮られる麺なんかは,ものである.わざわざ私がいなくても,これらのものはその場にあるのだろうから,世界はものの集まりという面もあるではないか.
ここから引き出した結論は,世界は私があってこそ存在する,という概念だ.「私の世界」である.これは即時に「世界は一つではない」ことを導く.「人の数だけ世界はある」ことになる.だから,仮に様々な世界を比べたとすると,各々の世界が持つ事実の量も内容も全く異なることが容易に予想される.私の世界における事実は,あの人の世界では事実ではなかった.それは単に知らなかったということでもあろうし,事実と認めたくないとか,事実とは思えないとか,事実と認知することができない状態である,などの事情が想定できる.「その場」がそれぞれ違う空間なのだから,世界は違っていてしかもたくさんあるのは当然すぎる.それなのに,世界はすでに決まっている.どういうことだろう.
おそらく,世界をものの集合とみた時に,世界はその場を通りかかる人たちにとって同じような世界になる.感覚が異なる可能性を残しつつ,その場にあるものは人によってそう大きく異ならないからだ.しかし,その世界は人により異なっている.なぜなら,人はものから事実を起こすからだ.人でなくても,ものから事実を起こす存在であれば,ものを使って,あるいはものを描いて,語って,動かし組み替えて,事実を生むのだ.世界は確かにものの集合であろう.しかし,ものから世界を起こす存在がたくさんいるので,世界はそれぞれにとっての事実を起こし,その場に居合わせたそれぞれにとって,それぞれの受け取り方で認知した事実からそれぞれの世界に追加するのだ.津波に遭遇した人は,地震が来れば津波が来ることを予期するだろうけど,津波を体験していない人の中には,例え海岸で地震に遭遇しても,津波を予想できない人もあるだろう.なぜなら,津波が来た状況を体験したという事実が世界に加わっている人にとって津波は「その場に起こされること」であるが,津波を知らない人にとっては「その場に起こらないこと」のうちに入っているだろうから.
故に,どれくらい知っているか,どのくらい体験してきたか,が世界を広げるために重要だ,という結論にもなる.しかし,世界に眠っている事実は多い.仮に,現在から人類史の起源まで遡って人類各人が世界に持っていた事実の総量を考えても,世界に知られずに眠っている事実の量の方が圧倒的に多いに違いない.各人の事実を引き比べて,何が正しいか検証したとしても,その検証が万人永劫の事実になる可能性はかなり低い.古典力学が確立したという現代でも,数値的にきれいに解けない問題があるように.であるから,論考1章で述べられた世界の定義に沿って世界を完全に持つことは,誰であろうと達成できるものではない.つまり,世界を完全に持つことができない.完全な世界を持つのは不可能なのである.
世界がひとつでない上に,どの世界も完全にはならない.しかし世界は厳然と存在し,ものは動き続ける.私たちは世界から事実を作り,世界に加え,変え,編集し訂正し更新する.そうしてみると,終章の「語りえないこと」とはなんなのか.私はこれに続く「沈黙しなくてはならない」がまた引っかかり続けた.どうして「沈黙しなくてはならなくなる」「沈黙せざるをえない」「沈黙してよい」ではないのか.沈黙は義務なのか,ならばそれはなぜか.この点に関しては,少し自由に捉えることにしている.つまり,沈黙する自由はあると思うし,沈黙させられる,沈黙するしかなくなる,という自発や了解の意味でもある.そう読んでいる.そりゃ,語れないことはもちろん語れない.語れないのだから.しかし,語れない状態にとどまれ,とは書いていない.むしろ,語れるようにしていこう,と世界が開ける方向を読み取れる.なぜなら,世界は例えどんな豊穣な世界であっても完全にはならないのだから,どんどん事実を増やして語れるようにしていったっていいし,逆に世界を制限し,事実を減らしたり規制することで,沈黙を守ったっていいはずだ.
そう思うと,論考で示された世界とは,ひとつの機械的な体系であって,この機構によって世界はできているという意味にはなっても,「沈黙するしかない,だから世界とはその場に起こることの全てなのだ」と始めに戻ってくるような内容を持っている気がしてくる.誰でも,厳然と存在する事物の総体の中を生きている.そして誰でも,その中で世界を起こして生きている.事物を使って事実を加えている.日々生み出している.事実はいくらでも生み出される.ひとつの事物からでも,事実はいくらでも生まれうる.つまるところ,世界とは思い出である.事物そのものは語りえない.世界を構成しない.事物は世界に組み入れられない.しかし,事実ならば世界に加わる.事実は語れる.語りえないこととは事物のことである.おそらく誰でも,事物と沈黙の次元には生きられない.事実と世界の次元こそ,私たちの生きている現実なのだ.